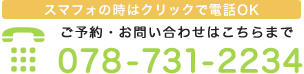下痢のお話 感染性腸炎
- 2025/01/13
- 便秘の話
今回からは下痢のお話をしようと思います。下痢とは糞便中の水分量が200ml/日以上または水様便を3回/日以上排出するときと医学的には定義されていますが、実際には便の軟化や水様化 排便回数の増加など患者の自覚症状で決めることが現実的です。
下痢にも急性下痢(14日以内)と慢性下痢(30日以上)があり、原因によって細かく分けられています。
今回は急性下痢について書いてみます。
急性下痢の原因ははほとんどが細菌やウイルスによるものであり、罹患部位により症状が異なり、小腸型と大腸型におおまかに分けられます。
1)小腸型 ウイルスや毒素を産生する細菌により腸管からの水分の分泌が増加して水様性下痢と悪心 嘔吐が主な症状です。
a)ノロウイルス:これはカキやアサリなどの貝についており、生や加熱が不十分なまま食べると感染します。 食べてから12時間~2日の潜伏期間ののち発症、感染力が非常に強く少量のウイルスでも感染するので、吐物や便の処理でウイルスが手に付着したままだとドアノブやリモコンのスイッチなどに触ることでウイルスが付着してしまい、それを触った人が口や鼻に触れることで感染することもあり、吐物などの処理後は流水と石鹸で30秒以上丁寧に洗うことで必要です。アルコール消毒は効かないのでご注意ください。また床などに付いた排泄物は大量のウイルスが残っているので、水拭きだけでは感染源として危険です。次亜塩素酸ナトリウム(家庭用漂白剤や次亜塩素酸の消毒液もあります)が有効です。 症状は嘔吐 下痢 腹痛など強烈ですが2-3日で自然軽快することがほとんどで、後遺症も残りません。特効薬はなく、脱水にならないよう十分な水分補給と対症療法が主な治療になります。
b)ロタウイルス:口からの経路で感染します。2-4日の潜伏期ののち激しい下痢と嘔吐 発熱や腹痛もみられます。 ロタウイルスは一般的なウイルスで生涯に何度も感染しますが、大人は次第に免疫ができて、症状が軽く済んだり、無症状のこともありますが、初めて感染する小児では強く症状が出ることがあります。これも特効薬はなく、脱水の予防をメインに対症療法となります。 感染力が強いのでノロウイルスと同様の対処が必要です。
c)腸炎ビブリオ:海水温の高い夏場に魚介類に付着しており、生食により感染します。摂食後12時間ほどの潜伏期ののち、激しい腹痛と下痢で発症します。1-2日ほどで自然軽快するので、脱水の予防を中心に対症療法がおこなわれます。
d)腸管毒素原性大腸菌:病原性大腸菌には種類によって毒素を出すものから腸粘膜に侵入して出血させるものがあり、菌の種類によって病状が異なります。このタイプは腸管内で増殖し毒素をだすことで下痢 嘔吐 腹痛を来たします。潜伏期間は12時間から3日です。症状は対症療法で1-3日ほどで軽快することが多いのですが、人により長引くこともあります。
e)ウェルシュ菌:どこにでもいる菌であり、肉類や野菜などに付着しています。カレーなどの煮物で一旦加熱されると菌は減りますが、常温で放置していると熱に強い芽胞を形成してどんどん増殖します。芽胞は100度で加熱しても滅菌でません。これを食べてしまうと6-18時間の潜伏期の後菌が産生する毒素によって腹痛と下痢で発症します。対症療法で軽快することがほとんどです。2日目のカレーなどは調理後常温で放置せず冷蔵庫で保管しておきましょう。
2)大腸型 大腸や下部小腸に感染した細菌が直接腸粘膜を障害して腹痛 発熱 渋り腹などが起こり症状も小腸型に比べ重いことがあります。潜伏期間も長めなので原因を忘れていることもよくあります。
a)サルモネラ菌:とり 牛 豚などの家畜の腸内に常在しており。特に鶏卵や加熱不十分な肉から感染します。感染すると12ー72時間ほどで腹痛 下痢 嘔吐 発熱 粘血便などで発症します。対症療法で数日で治ることもありますが、抵抗力の弱い人では重症化して敗血症をおこし生命の危険な状態になるため、ニューキノロン系の抗生物質を使うこともあります。 サルモネラ菌は感染しても発症せず、体内で生存して排菌し続けることがあり(健康保菌者といいます)二次感染の原因となります。 昔アメリカで実際にあった話ですが、ある女性が務めた先々の飲食店やお邸などで食中毒が多発し調査したところサルモネラの健康保菌者であった事例があります。日本の飲食業界では従業員の定期的な検便を行い、陽性者は除菌できるまで出勤できないこともあり予防策が講じられています。
b)キャンピロバクター:とり 牛 豚などの家畜の腸内に常在しており、生食や加熱不十分な肉から感染します。少量の菌量で発症するので菌の付いた手や調理器具からも汚染源になります。潜伏期間も2-5日と比較的長いので食べた本人もわすれていることもあり、当院での印象ですが問診で1週間ぐらい遡って食べたものを聞くと、鳥の刺身 たたきなどを食べた方が半分くらいはおられます。 症状は下痢 腹痛 嘔吐 ひどければ血便などを生じます。1週間ほどで軽快していきますが、症状の重い人にはマクロライド系の抗生物質を用います。
c)腸管出血性大腸菌:加熱が不十分な肉(特に牛肉)や井戸水などが感染源となることがあります。感染力が強く通常の食中毒菌では 100万個ぐらいで感染が成立しますが、この菌は100個ほどで感染が成立しますが、加熱に弱く75度 1分ほどで感染力は消失します。潜伏期間は2-9日と長く、激しい腹痛と下痢から始まりのちに血便 下血となり重症化することがあります。腸粘膜に侵入し、ベロ毒素という強力な毒素をだします。この毒素は腎障害 貧血などを起こす溶結性尿毒症症候群を引き起こすことがあります。治療は脱水の予防のため輸液と対症療法と抗生物質になります。
このほかにも原因微生物は多数ありますが、代表的なものを挙げてみました。感染性下痢の参考になれば幸いです。